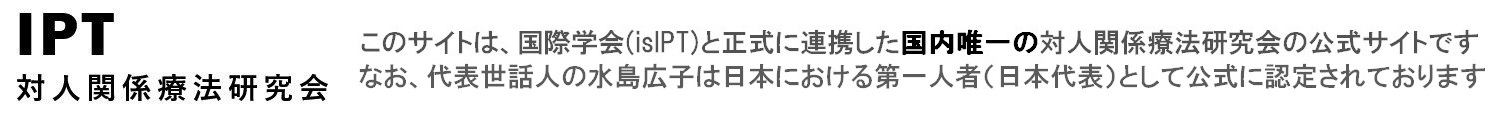対人関係療法研究会の皆様へ
臨床現場でご尽力されている皆様に少しでもお役に立つ情報をお伝えできればという思いで、定期的にIPT-JAPAN通信を発行しております。IPT-JAPAN通信Vol.17では、8月に東京で開催された日本トラウマティック・ストレス学会プレコングレスに参加した海野先生の感想、IPT実践でよく寄せられるQ&A、そして7月と9月に開催された実践応用編(9月の実践応用編では、初めて「IPTのエッセンス」を取り入れて実践した症例について検討を行いました!)に参加された方々の感想を紹介します。
IPT-JAPAN通信編集委員会
○●日本トラウマティック・ストレス学会 プレコングレスに参加して●○ 世話人 海野 素麗
2025年8月1日に行われた、日本トラウマティック・ストレス学会のプレコングレスに参加いたしました。
学会で初めてIPTが教育的ワークショップとして扱われ、井野敬子先生のファシリテーションのもと、利重裕子先生、前川浩子先生、岩井圭司先生らがIPTの概要→PTSDへの適用→症例提示を一連で示されました。
<所感>
今回、IPTが日本トラウマティック・ストレス学会の独立枠として初登場したことは、国内の臨床にIPTを根づかせてきた代表世話人・水島広子先生の長年の牽引やIPT-JAPANの研究会で重ねられてきた地道な発信と学術・教育活動、そしてその志に賛同し臨床で磨き続けてきた多くの実践家の努力の結晶にほかなりません。
IPTが体系的に紹介され、具体的な症例まで提示された意義は大きく、患者さんや今後IPTを実践する臨床家にとっても重要な位置づけになったと思います。
講義の中で、代表世話人・水島広子著『トラウマの現実に向き合う—ジャッジメントを手放すということ』の紹介があり、初心を思い出しました。私は臨床家である前に1人の人間として、幾度もこの本に支えられてきました。「ジャッジメントはある人の主観に基づく評価」と述べられていますが、トラウマ・PTSD治療において、評価を手放す姿勢は重要であり、「治療者は“病気の専門家であって、人間の専門家ではない”」という一節は、IPTの核心と響き合います。私はIPT治療者として、患者さんと共同研究者として対等に理解を深めたいと思っています。水島先生は、IPTは全人的にとらえていく治療であり、症例を大きくみることが肝要だと言っています。私は面接の場で「人間っていいもんだ/本当に力のある存在だ」と感じる瞬間が確かにあります。学会参加は初めての体験でしたが、先生方のご発表で多くが腑に落ち、現場に持ち帰れる具体度でIPTが示されたことに心強さを覚えました。ありがとうございました。
今年12月に開催されます「日本公認心理師学会学術集会(東京大会)シンポジウム」で、IPTの症例を発表する機会をいただきました。これらの学びを基に、ケースフォーミュレーションや治療プロセスの実際を示し、つなげてまいりたいと思っております。
<ワークショップの内容のまとめ>
IPTには実証的なエビデンス(RCT、メタアナリシス)があり、トラウマ体験には踏み込まず、「現在の対人関係機能と感情のつながり」に焦点をあてるアプローチのため、曝露中心の第一選択群(トラウマ焦点化心理療法など)を十分に補完し、トラウマ体験を語ることが難しい/語ることで不安定になる当事者にも届く、治療の選択肢となり得る点が強調されました。
そして、IPTの歴史や基本的な考え方において、クラーマンらが急性期うつ病に対する薬物療法の期間と精神療法を研究する中で、構造化された精神療法(当初は「ハイコンタクト」と呼ばれた)が開発され、さらなる研究を経て「対人関係療法」として確立されました。IPTは多元モデルの考え方を採用しており、実証を経て、症状と対人関係は相互に影響し合うことを説明されました。
IPTの構造については、初期で治療の基礎(病歴聴取、医学モデルの採用、対人関係質問項目の聴取、4つの問題領域への焦点化、フォーミュレーション等)を作り、中期で問題領域に取り組み、終結期で治療の地固めと将来への備えを行うこととなります。IPTの特徴は、期間限定であること、治療終了後も効果がじわじわと伸びる点、そして治療者のあたたかい姿勢と患者さんとの共同研究者としての関係性が重要だと強調されました。私自身、IPTのファンである理由はこのあたりだと思います。
また、持続エクスポージャー療法(PE)など、トラウマ焦点化心理療法が過去のトラウマ記憶の再処理を主とするのに対し、IPTは現在の対人関係に焦点を当てます。IPTは感情の再調律とソーシャルサポートの構築を目標にし、宿題がないことなど、うつ病併存例での中断率の低さが示されました。
症例提示では、単回性PTSDの症例を役割の変化でフォーミュレーションをし、決定分析では沈黙場面での扱いを、ロールプレイを通じて感情表現の練習を行うことをご紹介いただきました。
複雑性PTSDの症例提示では、ICD-11の複雑性PTSDの枠組み(PTSD基準とDSO基準を満たすものとして定義)を踏まえ、医学モデルを採用し、安心できる治療関係の構築や、感情の同定と言語化を支援、家族内における感情表現を促し、理解を得ていく経過が共有されました。
○●IPT実践におけるQ&Aコーナー:「対人関係」というキーワードの考え方●○ 世話人 前川 浩子
これまでの実践入門編や実践応用編を通じて、IPTの実践に関心を寄せてくださる方が多くいらっしゃることをとても嬉しく思っております。国際対人関係療法学会(isIPT)では、IPT実践者・研究者のことをIPTerと表現することもあるのですが、日本でもIPTのファン、IPTerがさらに増えることを願っています。
皆様がIPTを実践される上で、Tips(ヒント)があるとお役に立てるのでは?と考えまして、このコーナーを担当することになりました。わくわく。今回は、IPTのキーワードである「対人関係」という言葉について、次の二つのQuestionから考えてみたいと思います。
Q1:対人関係に問題があれば、IPTは適用できるのですよね?
A1:必ず適用できるとは限りません。適用できないこともあるんです。。。
ご存じのように、IPTには診断が必要です。IPTは医学モデルに基づいていますから、病気の症状がある方に対してまず診断を行います。そして、病者の役割を与えるところからIPTが始まります。また、あらゆる精神疾患に対してIPTを適用できるわけではなく、現在、エビデンスがあるとされているものに対して適用するということになります。精神的な困難さ、心理的支援を求める方の中には対人関係の問題を抱えていらっしゃるケースは確かに多く見受けられます。「対人関係に問題があるからIPTが効くのでは?」と思うこともあるのですが、その方がIPTを適用できる診断のある方なのか、ということはポイントです。IPTはその病気の症状と対人関係の問題の関連性を扱う精神療法ですから、対人関係の問題だけでは、アプローチができませんよね。診断がついた病気の症状と対人関係の問題の両方が必要となります。一方、診断はつかない程度の閾値下のうつ症状の場合は、IPC(対人関係カウンセリング)を適用できる場合もあります。
Q2:表面上、対人関係に問題がなさそうな方にはIPTは適用できないんでしょうか?
A2:そうとも限りません。よーく、お話を聴いてみましょう。
先ほどのQ1の裏返しのような質問です。診断がつく症状はあるけれど、でも、対人関係上の問題はなさそう、、、IPTはできないのかな、というケースもあります。病気の状態だと、対人的な交流がなく、そのため問題も生じていないということは考えられます。しかし、病気になる前はどうだったのか、ということもお話をお聴きして、あてはまる問題領域がないか探してみましょう。「欠如」の問題領域は、IPT治療の初心者には確かに難しいのですが、それ以外の問題領域が当てはまるかもしれない、と可能性を探ることは意味があります。対人関係の出来事と症状の変動が現れる、研究会でよく出てくる「にょろにょろの図」(症例概要図)で表現できないか、挑戦してみてください。また、一見対人関係の出来事に見えないライフ・イベント(生活上の出来事)であっても、そこにソーシャル・サポートの変化がなかったか、などという目で見ていくと、例えば「役割の変化」という問題領域を見出すことができる場合もあります。
実は私自身も、うつ病の患者さんにIPTをはじめたのですが、IPTの初期でうつ病の発症と関連のある対人関係の出来事をみつけようと思ったときに、「あれっ?対人関係に問題がないかも、、、どうしよう?」と思うことがありました。患者さんご自身の考え方や認知に関係するお話が多いときに焦ります。ただ、落ち着いて、「どんなときに、そう思われたのですか?」とお伺いしてみると、親とのやり取りの中でそう感じられて落ち込みがあったことがわかってきて、「やっぱり、うつ病の発症には人との関係と関連がありましたね♪」と患者さんと一緒に再確認した出来事もありました。
IPTは「対人関係」がキーワードです。ともすれば、私自身もこの用語に振り回されそうになることがありますし、様々なケースにIPTを適用したい!と思ってしまうこともあります。しかし、IPTは治療の選択肢の一つにすぎません。IPTは治療者が行いたいから適用するというものではなく、患者さんにとって最適な治療はどれかを治療者が考えることも大切だなと日々感じています。
とはいえ、多くのIPTファンの皆様がIPTを実践されるにあたってIPT-JAPANでは様々なご支援をしたいと考えております。ぜひ、IPTの適用に迷われましたら、実践応用編の「IPTエッセンス枠」で症例をお出しくださいませ。お待ちしております。
○●ワークショップ開催報告●○ 世話人 岩山 孝幸
7月・9月の実践応用編では、IPT適用の検討や、難しいケースに対してIPTのエッセンスをどのように活かせるのか、についてディスカッションが活発に行われました。以下に、それぞれの感想をご紹介いたします。
実践応用編(2025年7月27日開催)
当日は難しいケースにIPTを導入する際に気をつけることなど、重要な臨床的判断に触れる機会となり、参加者からは「IPTの適用が難しいケースを検討することで、IPTの強みや特徴への理解が深まった」との声が寄せられました。また、治療者の言葉選びや伝え方の工夫が具体的に示され、「クライエントへの言葉の選択が日々の臨床の参考になった」「普段の面接でも伝え方を工夫していきたい」との感想もありました。IPTのエッセンスを活かした臨床を行っている参加者からも「毎回フレーズや聞き込み方が参考になる」との感想をいただきました。
実践応用編(2025年9月21日開催)
身体症状症のケースや発達特性を抱えるケース、さらには解離を伴う複雑なケースが検討され、IPTの適応や限界を見極める視点が深められました。参加者からは「IPT適用が難しい症例でも、治療の流れを意識することでアセスメントや情報収集に役立つ」「IPTの適用がない場合でも、そのエッセンスを活かせる」といった声がありました。また、「I(アイ)メッセージが必ずしも有効ではないケースがある」「ASDや自己愛傾向の方への対応は日常臨床にも直結する学びだった」との感想も多くいただきました。さらに、さまざまな職種の方にご参加いただいたことで「多職種ならではの多角的な議論が得られた」「普段気づかない視点をいただけて有意義だった」といった感想も寄せられました。
○●編集後記●○
最後までニュースレターをお読みいただき、ありがとうございます。今回は、国際双極症学会(ISBD)に出席した際の率直な感想を記したいと思います。
今回の学会では、ISIPTの仲間はもちろん、Psychological Interventions タスクフォースの先生方とも直接交流することができ、非常に有意義で刺激的な時間となりました。普段はオンラインでしか交流できない海外の先生方に実際にお目にかかれるのは、やはり国際学会ならではの貴重な機会だと改めて実感しました。そして、このような機会につながるサポートをしてくださった諸先輩方に、心より感謝申し上げます。
また、今回の学会では、ISIPTメンバーが代表し、IPSRTのアジアにおける文化的適応について発表されました。文化的適応は、国単位はもちろん、地域単位や世代・性別といった属性単位の視点からも考える必要があり、大変重要なテーマだと感じています。
さらに、私が参加しているPsychological Interventions タスクフォースは、双極症の研究者・臨床家コミュニティをより強く結びつけ、心理的介入の開発において国際的かつ広範な協力体制を構築し、資源を節約し、研究の質を向上させることを目的としています。私がこのタスクフォースに加わったのは、文化的背景の異なるメンバーが加わることに意義があると伺っているからです。したがって、双極症の心理的介入の開発においても、多様な文化的背景を踏まえて取り組むことが極めて重要であると考えられています。
最後になりますが、今回のISBDでの諸外国の先生方との直接交流を通じて、文化の違いを含めて相手を理解し、互いに尊重し合うことこそが、人間関係を築く土台になるのだと強く感じました。そして、それは普段の家族や仲間との人間関係、診療における患者さんとの関係にも通じることだと改めて感じました。
※ このメールには返信ができません。ご意見、ご要望がございましたら、下記までお寄せください。
IPT-JAPAN通信 編集委員会 担当メールアドレス: letter@ipt-japan.org
○●——————————————————————————-●○
IPT-JAPAN通信 編集委員会
〒106-0046 東京都港区元麻布3-12-38
FAX: 03-6673-4173
URL:http://ipt-japan.org/
○●——————————————————————————-●○