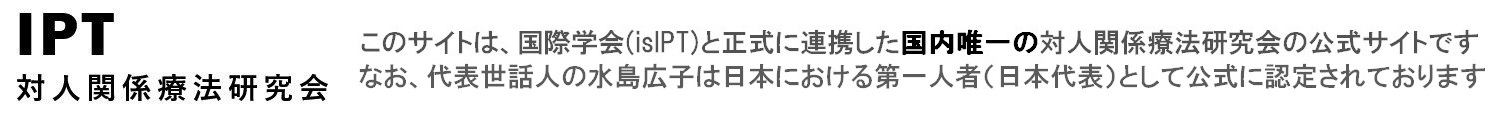※研究会メーリングリスト配信版と比べ、画像を一部割愛しております。
対人関係療法研究会の皆様へ
新年あけましておめでとうございます。臨床現場でご尽力されている皆様に少しでもお役に立つ情報をお伝えできればという思いで、定期的にIPT-JAPAN通信を発行しております。IPT-JAPAN通信Vol.15では、まずPTSDのためのIPTの治療開発者であるジョン・C・マーコウィッツ自身によるレビュー(後編)をお伝えします。続いて、水島による「役割の変化」と「医原性(治療による)役割の変化」、2024年後期 IPT研修会開催報告についてお伝えいたします。
IPT-JAPAN通信編集委員会
○●文献紹介●○ 世話人 大石 康則
IPT通信では、毎号、IPTに関する様々なトピックや重要な文献などを紹介しています。
今回ご紹介するのは……
心的外傷後ストレス障害(心的外傷後ストレス症)に対する対人関係療法:エビデンスの批判的レビュー
Interpersonal Psychotherapy for Posttraumatic Stress Disorder: A Critical Review of the Evidence.
John C. Markowitz, MD
J Clin Psychiatry. 2024 May 29;85(2):23nr15172.doi: 10.4088/JCP.23nr15172. PMID: 38814110
前回のIPT通信では前半部分(PTSDに対するIPTの概要+民間人を対象とした研究のレビュー)を紹介しました。今回はその続きです。
(B)退役軍人を対象とした研究
退役軍人に対する治療法として、IPTはエビデンスに乏しい。米国退役軍人管理病院システムは、PTSDに対する治療法として曝露療法を指導し、IPTは適応ではないとした。
2007年、ロバートソンらは独自のマニュアルを用いて、13人のオーストラリア人PTSD患者を対象に8セッションのグループIPTを行った(オープン試験)。患者はほとんどが男性で、平均年齢は54歳。安定した薬物療法を受けており(92%がSSRIを内服)、54%が戦闘トラウマを訴えていた。PTSDの回避性クラスターでは症状が中等度に軽減したが、侵入性クラスターと過覚醒性クラスターでは有意な軽減はなかった。患者は社会的機能と抑うつ症状の改善を報告し、その改善は3ヵ月後の追跡調査でも持続していた。効果は緩やかであったが、IPT群は全般的なウェルビーイングと対人関係機能が向上したと、著者らは結論づけた。
2010年、レイとウェブスターは認知行動療法に反応しなかった56~75歳のオーストラリア人ベトナム男性退役軍人9人を対象として、グループIPT研究を行った。8名が抗うつ薬を安定して内服。彼らは、独自のマニュアルに従って8週間のグループIPTの効果を評価した。患者は改訂出来事インパクト尺度(IES-R)のPTSD症状で有意な改善を示したが、統計学的に有意な改善を示したのは9人中2人だけであった。そのうち1人は2ヵ月後の追跡調査で悪化していた。患者は抑うつ症状が緩やかに減少し、対人関係機能が改善したと報告した(P=.51)。
軍事的性的トラウマは、特にひどいトラウマの変種である。幼少期にトラウマを持つ人の多くは、虐待的な家庭から逃れるために、信頼できる仲間や秩序ある組織を求めて、入隊年齢に達するとすぐに米軍に入隊する。こうした「仲間」から暴行を受けると、トラウマと不信感が増幅する。
2016年、Krupnickらは退役軍人管理局で15人の女性退役軍人にPTSDの治療を行った。15人の女性のうち87%がアフリカ系アメリカ人であり、7%が白人であった。平均年齢は39.9歳。その15人中12人が軍隊での性的トラウマを報告している。うち9人はうつ病を併発していて、1人は双極性障害(双極症)を患っていた。10人の患者はKrupnickらのグループIPT(Krupnick JL, et al. Psychother Res. 2008;18(5):497–507)から12セッションの個人IPTに移行し、完遂した。PTSD症状は、PTSDチェックリスト(PCL)が67.9から55.5へと臨床的に有意な減少を示し、ベック抑うつ質問票(BDI)スコアは35.1から28.9へと減少した。これらは3ヵ月後の追跡調査でも効果は維持された。PTSDの診断基準を満たさなくなったのは3分の1程度で、この結果は軍人における曝露ベースの治療に匹敵すると著者らは論じている。
ピックオーバーらは、米国退役軍人35人とその家族15人を対象に、14週間のPTSDに対するIPTを実施した(オープン試験)。退役軍人の3分の2、そして14人の家族が、PTSDにうつ病を併発していた。患者の半数以上が薬物療法を受けていた。対象の退役軍人は80%が男性で、白人53%、アフリカ系アメリカ人20%、その他27%。33%が既婚者であった。退役軍人の脱落率は、家族の脱落率よりも高かった。退役軍人のPTSD臨床診断面接尺度(CAPS-5)スコアは34.8から14週後に20.2、3ヵ月後の追跡調査では18.9に低下した。ハミルトンうつ病評価尺度(HAM-D)のスコアは、これらの期間で14.6→11.1→9.4と減少した。家族も同様の改善を示した。この研究において、PTSD患者は分離不安を併発しており(69%)、IPTを実施することで分離不安の割合が低下したことから、不安定な愛着と感情調節不全の修復がIPTの治療メカニズムである可能性が示唆された。
合計72人の退役軍人を対象としたこれら4つの試験は、IPTが民間人と同様に退役軍人にも有効であることを示唆している。これらの臨床試験からの脱落率は、残念ながら退役軍人によく見られるように、民間人よりも高い。対象の61%が男性であった(Krupnickらの試験の女性15名を除くと77%が男性)。これら小規模試験のほとんどで、2~4ヵ月の追跡調査期間中も効果が維持された。
オープン試験ではIPTの有効性が証明できないため、IPTと曝露に焦点をあてた治療のランダム化臨床試験の実施が求められている。ありがたいことに、2件が進行中である。コーネル大学医療センターのDifedeらは、軍事的性的トラウマによるPTSDを発症した退役軍人を対象に、持続エクスポージャー療法(PE)とIPTを比較する臨床試験を開始した。
シアらは、2つの退役軍人病院において、退役軍人のPTSD患者に対するIPTとPEの最初の同等性試験※を実施した。対象者は、50分の個人セッションを12回行うIPT群(n=61)と、90分のセッションを12回まで行うPE群(n=54)に無作為に割り付けられた。参加には、戦地でのトラウマによるPTSDと診断され、CAPS-5のスコアが23点以上であることを条件とした。患者は男性115人、平均年齢49歳で、ほとんどが中東戦争への派遣を報告していた。患者の約半数が現在、77%がうつ病を患った経験があった。脱落率はIPTが26%、PEが49%であった。CAPS-5のスコアは、IPTでは36.3点から27.8点へ、PEでは34.8点から28.2点へと、どちらの治療法でも低下した。群間効果サイズ0.26はIPT群に有利であり、CAPS-5反応率(10点以上の改善と定義)も50%対31%であった(有意差なし)。治療前後におけるCAPS-5の改善は統計学的に有意であったが、ほとんどの完遂者ではかなりの症状負担が持続していた。
IPTが対人関係や職業上の機能、QOLを向上させるという研究者たちの仮説は、実証されなかった。両治療とも、関係性の機能不全を評価するInventory of Interpersonal Problems-32では、比較的に緩やかな改善であった。治療終了時、3ヵ月後、6ヵ月後の追跡調査においても、治療成績に統計学的有意差は認められなかった。登録されたサンプルサイズでは、統計的な同等性を正式に実証するには不十分であったが、同等性仮説ではなく非劣性仮説を検証していた場合、IPTのPEに対する非劣性が実証されていたであろう。
※同等性試験とは、新しい治療法(今回の場合には、IPT)が既存の標準治療(今回の場合にはPE)と同等であることを証明することを目的とする試験
このように、シアらはマーコウィッツらが民間のPTSD患者に対して行った知見を、退役軍人に対しても再現した。シアらは、併存するうつ病や性的トラウマなどの潜在的な調整因子をまだ評価していない。この研究には、募集人数が予定より少なかったなどの限界があったが、それにもかかわらず、退役軍人のPTSD治療においてIPTがPEに匹敵することを示したという点で、画期的である。
シアらの試験の61例を加えても、IPTによる治療を受けた退役軍人の総数はn=133と少ない。報告された5つの臨床試験の脱落率は0%から37%であった。
全体として、積極的治療と比較したRCT(n=3)では、IPTの脱落率は25%(35/140例)であったのに対し、PE、リラクゼーション療法、セルトラリンでは39%(63/159例)であった。
(画像ファイルは割愛)
ディスカッション
IPTは、これまでに有効とされた他のPTSD治療と同等の効果があると思われるが、試験の数や規模はまだ小さい。成人を対象としたものでは、ネガティブな結果だった臨床試験はない(ただしSchaalらは、ルワンダのジェノサイド孤児26名を対象とした小規模な臨床試験において、IPTはナラティブ療法よりも効果が低かったとしている)。IPTは、個人でもグループでも様々なトラウマをもつ民間人や退役軍人の治療に役立っている。まだ断片的なデータではあるが、PTSD患者の約半数に併存しているうつ病に対して、IPTが治療上の利点がある可能性が示唆されている。このような併存症のある患者は、治療がより困難であり曝露療法に耐えられないと感じている可能性がある。曝露療法は、少なくとも理論的にはトラウマが終わったことに依存している。つまり、過去は過去、現在は現在であり、トラウマを思い出させるものに直面しても安全である、という前提である。例えば、現在進行中の家庭内暴力は、曝露の禁忌としてよく挙げられる。曝露療法は、ウクライナや中東で現在も続いている戦争に巻き込まれている人々のような、継続的なトラウマに直面しているPTSDの割合が高い集団に有効であろうか? 曝露に頼らないIPTは、そのような人々にとって利点があるかもしれない。
理論的には、曝露療法はPTSDの再体験症状により大きな効果をもたらし、IPTは社会的機能により大きな効果をもたらす可能性がある。しかし事実として、これまでの研究では症状クラスターにおける特異的な利点は見つかっていない。むしろ、曝露、薬物療法、感情焦点療法など、どのようなメカニズムによる改善であっても、全般的な改善と症状の軽減をもたらすようである。
現存する研究の数が少ないため、このレビューには限界がある。また、非メタ分析的アプローチであるため、研究間の影響の正確な推定ができていない。つまり、さらなる研究が必要である。米国国立精神保健研究所(NIMH)は、残念ながらこのような臨床試験に資金を提供していない。van Dijkが主導するオランダの大規模研究が進行中であるが、この研究では、まずPTSD患者をPEかEMDRのいずれかに無作為に割り付け、その後、最初の治療で反応しなかった患者をもう一方の曝露に焦点を当てた療法かIPTのいずれかに再度割り当てている。われわれは、IPTが曝露に反応しなかったPTSD患者の治療に有効であると予想している。
PTSDマニュアルは若干異なる場合もあるが、いずれもIPTの基本テンプレートを踏襲したものである。同様に、セッション数にも多少のばらつきがあり、週1回50~60分の個人セッションが12~14回、2時間のグループセッションが8~16回であった。このような違いはあるが、調査結果はほぼ一致している。現在、複数の独立した研究チームが無作為化試験を実施し、IPTの有効性の基準を満たす肯定的な結果を得ている。限界があるにせよ、IPTで得られた知見の積み重ねは、広範な臨床的意味を持つ。この分野は現在、IPTがPTSDに効くかどうかという問題を乗り越え、少なくとも民間人と退役軍人の集団において、いくつかの可能性のある利点とともに、IPTが効くという説得力のあるエビデンスへと移行している。IPTはまた、急性心的外傷を負った民間人女性に対するSSRIに匹敵する効果を示した。IPTが他の第一選択の介入と同等であることは、PTSD治療の形を再構築し、曝露しない重要な選択肢を提供するものである。
何年もの間、PTSDの心理療法には曝露が不可欠だと考えられてきた。しかし、すべての患者やセラピストがそれを望んでいるわけではない。患者にとって、それは最大の恐怖に直面することであり、うつ病の併存がその難題をさらに悪化させる可能性がある。退役軍人管理局のシステム全体を通して、PEと認知処理療法の研修を意欲的に展開したが、ほとんど受け入れられず、その魅力の限界を示している。
退役軍人管理局の治療ガイドラインは、IPTの適応に関して揺らいでいる。2017年のガイドラインでは、軍人患者に対するIPTに関するデータがあまりないにもかかわらず、IPTを弱く推奨している。だが2023年からの最新のガイドラインでは、その推奨が削除された。その理由のひとつは、IPTに関する研究には、「臨床医が報告するPTSDという重要なアウトカムを含むものがない」という誤った主張に基づいている。最近のシアらの研究は言うに及ばず、民間人を対象とした臨床試験から得られたエビデンスの増加は、この決定に疑問を投げかけている。退役軍人管理局やその他のガイドラインは、PTSDに対するIPTの推奨を検討すべきであり、また、退役軍人管理局以外の環境で退役軍人を治療している私たちが発見したように、PTSDに対するIPTがより忍容性の高い別の選択肢であるとして、臨床医を訓練することさえ検討すべきかもしれない。さらに、地域社会の患者は、曝露療法とは別の選択肢として、エビデンスに基づきかつ感情に焦点をあてたPTSDの治療を求めるかもしれない。
○●「役割の変化」と「医原性(治療による)役割の変化」●○ 世話人 水島 広子
このところ、問題領域を「医原性(治療による)役割の変化」とするフォーミュレーションをしばしば見かける。病気だった自分から、健康な自分への「役割の変化」というニュアンスである。しかし、考えてみれば、基本的にどんな治療も「医原性(治療による)役割の変化」につながるものである。それが治療というものだ。
本来、IPTにおける「役割の変化」というのは、発症、あるいは増悪の「きっかけ」になったものを指す。何らかのライフイベントにより、病気が発症する、あるいは増悪する、という場合である。これは「4つの問題領域」の1つとして、開発された当初より歴史的に位置づけられてきたものだ。したがって、そのようなライフイベントが見つかれば、その問題領域は主に「役割の変化」ということになる(もちろんライフイベントの内容によっては「不和」や「悲哀」が選ばれることもある)。
一方、「医原性(治療による)役割の変化」という概念は、ジョン・C・マーコウィッツ(John C Markowitz)によって、DSM-IVの気分変調性障害 (DSM-5-TRでは、DSM-IVの気分変調性障害と慢性の大うつ病性障害を統合した「持続性抑うつ症」という診断名となっている。)向けのマニュアルの中で初めて提唱されたものである。気分変調性障害のような慢性的な疾患の場合、ライフイベントにより増悪することもあるが(その場合は主に「役割の変化」として扱える)、そのようなライフイベントが見つからず、基本的に症状がずっと持続している場合も少なくない。そのような場合、主に発症のきっかけを考える「4つの問題領域」の中には適したものが見つからないことも多い。そのようなケースの問題領域および治療目標を考える上で、「医原性(治療による)役割の変化」が提唱された。それまで自分の「性格の問題」「暗さ」と考えてきたものを、「病気の症状」として認識できるようになる、というのがその主なポイントである。「医原性(治療による)役割の変化」は気分変調性障害の治療においては基本的にすべての症例に通じるものであり、例えば「役割の変化」や「不和」が見られる場合にも、併存という形をとる(問題領域を2つ定める)ことも少なくない。その後のIPTの発展により、「医原性(治療による)役割の変化」は、社交不安症、慢性PTSDなどにも用いられるようになった。これらは気分変調性障害と同じく、症状が持続しており、「4つの問題領域」だけではフォーミュレーションできない疾患である。
このような流れを踏まえると、本来の「役割の変化」は、抑うつエピソードに代表される主にエピソード性のものにおける発症のきっかけ(あるいは慢性のものであっても、増悪のきっかけ)を示すものである。一方「医原性(治療による)役割の変化」は、もっと限られた概念で、「4つの問題領域」では対処できない、慢性的なものに対して用いられるものであると言える。ただし、慢性であっても、PTSDにおける対人過敏などは、PTSDの症状として心理教育の対象となるものであって、「医原性(治療による)役割の変化」とは考えない。
冒頭の問題意識に戻れば、私が懸念しているのは、「医原性(治療による)役割の変化」の濫用である。繰り返すが、どんな治療も「医原性(治療による)役割の変化」を目指したもので、それはIPT特有ではない。IPT特有の問題領域や治療目標を考える際には、まずは「4つの問題領域」を検討すること、そしてそれに当てはまらない慢性疾患の場合のみ「医原性(治療による)役割の変化」を考えるべきである。
○●2024年後期 IPT研修会開催報告●○ 世話人 岩山 孝幸
2024年後期も各種IPT研修会が開催され、多くの参加者の皆様から貴重な感想をいただきました。実践入門編・実践応用編・特別編すべての研修会を開催し、それぞれの研修会の特徴が反映された学びの場となりました。以下に各研修会の感想を抜粋してご報告いたします。
実践応用編(2024年9月29日開催)
複雑性PTSDや摂食障害など、難しい症例に対する治療プロセスを共有し、IPTの枠組みを維持しつつ、患者に寄り添う姿勢をどのように両立するかが学びの中心となりました。「IPTの適用が難しいケースであっても、治療プロセスを丁寧に進めることの大切さを再認識しました」「深刻な生育歴を持つ患者に対しても、IPTの原則を守ることで治療者自身も守られることが分かり、基本に立ち返る意義を感じました」といった感想が寄せられました。
実践入門編(2024年10月13日開催)
全国から100名にご参加いただきました。当日はIPTの基本的な構造や治療の進め方について、逐語録や症例ビデオを用いた研修を行いました。「ビデオを見ることで、実際にクライエント(患者)とどのように関わるかイメージが湧きました」「スタンダードな面接が難しい場合でも、IPTの枠組みを維持することで治療に活かせることが分かり、臨床応用への自信が持てました」との声が多く、IPTの基礎を実践に結びつけるための貴重な機会となっただけでなく、治療者の温かい姿勢や具体的な問いかけが、参加者の理解を深める機会になったようです。
特別編(2024年11月17日開催)
特別編はロール・プレイを通して、具体的なやり取りを体験しながら学ぶ演習形式で行われました。「不和の相手との同席面接など、新しい学びが多くありました」「感情を尊重しつつ、治療者のスタンスを崩さないやり取りが参考になりました」との感想が多く寄せられました。また、治療者がどのように患者の気持ちを確認しながら進めるかを実践的に学ぶ場となり、「クライエント(患者)役を演じることで治療者の言葉の影響を実感できた」「悲哀に焦点を当てたセッションの流れが理解できた」など、具体的な学びが得られたとの感想もいただきました。
これからも各研修会の特徴を活かしながら、参加者の皆様がそれぞれの臨床現場で活用できる学びを提供し、質の高いIPTを届けるためのワークショップを継続してまいります。
○●編集後記●○
最後までニュースレターをお読みいただき、ありがとうございます。2025年はIPT-JAPANの活動を一層充実させるため、定期的なワークショップ開催、通信での情報発信に加えて、スーパービジョン(SV)体制が始動いたします。IPTのSV体制に関しては、2024年に他国のスーパーバイザーから、ISIPTの基準を準拠した上で各国の状況に合わせたSV体制を共有していただきながら、日本での実施方法を模索しておりました。日本の現状を伝えつつ、他国の詳細なSV体制を把握することには相当な労力を要しましたが、2025年には皆様に進捗を報告できる運びとなり、嬉しい限りです。引き続き、国外のスーパーバイザーと意見交換を行ってまいりますので、SV体制以外にも、有益な情報がありましたら通信にてお知らせいたします。
2025年が皆様にとって健康と幸せに満ちた素晴らしい一年となりますようにお祈り申し上げます。そして、本年もIPTを一人でも多くの方に知っていただき、IPTを必要とする方々に届くように尽力してまいります。引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
※ このメールには返信ができません。ご意見、ご要望がございましたら、下記までお寄せください。
IPT-JAPAN通信 編集委員会 担当メールアドレス: letter@ipt-japan.org
○●——————————————————————————-●○
IPT-JAPAN通信 編集委員会
〒106-0046 東京都港区元麻布3-12-38
FAX: 03-6673-4173
URL:http://ipt-japan.org/
○●——————————————————————————-●○